前回に引き続いて、今回は、
「相手から何かを聞かれる会議」
の進め方です。
なにやら尋問や査問のような表現ですが、実際にはいろいろな会議がこのタイプに当てはまります。
「(発注者として参加する)要件、要求仕様のヒアリング」
「(チーム内の統括されるメンバーとして参加する)進捗会議」
他にも、
「プレゼンテーション後の質問タイム」
「(被レビューアとして参加する)各種レビュー」
なども変則的ではありますが、この「聞かれる」タイプの会議と言えます。
このタイプの会議は、「聞く会議」以上に、事前準備が大切となります。
会議の議題に関する下調べはもちろん、会議の中で関連する事柄にまで質問が及ぶことも珍しくないので準備はしっかりしておきます。
ただし、準備に費やす時間は、自分の抱える他の作業とのバランスには注意が必要です。
なぜなら、準備とは基本的に成果物がない作業だからです。
上司は少ない準備で最大の成果(会議がスマートに終わること)を望むので、こっそりしっかりが基本となります。
さて、実際に会議が始まります。
会議の最中に意識したいのが、
「攻守のフェーズ」
です。
会議の参加者の力関係というのはどうしても、お金を払う側や役職の高い側が強くなります。
ですが、ここで言う「攻め」と「守り」は、そういった立場上の強弱ではなく、
「自身を持って何かを説明している時は『攻め』」
「記憶があやふやだったり、後ろめたいことを隠したり避けたりしながら答えている時は『守り』」
といった、会議で説明している時の自分の状態をあらわしたものを指しています。
これを、客観的に把握できるように努めることが第一です。
会議の経験の浅い人や会議が苦手という人は、この自分を含めた会議の参加者を客観的に把握するのが苦手なことが多いようです。
自分が『攻め』ているのか、『守り』ながら説明しているのかが分かるようになると、次は、
「『守り』から『攻め』への転換」
が重要になってきます。
『攻め』続けて会議が終了できるのであれば、それはコントロールされた状態、または、コントロールが不要な状態といえるからです。
この、転換に有効なテクニックがいくつかあります。
「ズバっと謝る」
「(事前に準備した得意な、自信を持って説明できる内容に)話を切り替える」
「質問を切り返す」
一つ目が一番王道で一番有効です。
非を認めた時は、善後策や再発防止策まで打ち合わせることができれば、かなりカッチリした印象を与えることができると思います。
また、時には謝るついでにそれらについて教えを請うのもいいでしょう。
相手は得意になってしゃべりはじめ、いつしか追及の手は緩む、なんてこともあるかもしれません。
二つ目と三つ目はちょっと上級テクニックとなりますが、あまりやりすぎると「誤魔化し」と見なされます。
これらをクセでやってしまっている人も多いですが、そういう人は絶対周りから信用されないので注意が必要です。
また、『攻め』にも注意が必要です。
まず、
「誰かを攻撃しない」
参加者であろうとなかろうと、人を責めて得られるのはその場を制したという達成感だけで、必ず、最終的には自分自身を貶めることになります。
例えば進捗が芳しくない責任を他のメンバーに押し付けたとしても、結局上司はよい評価をしてくれず、「言い訳が多い、次回も改善が見込めない」などといった、マイナスのイメージを持ってしまいます。
他にも、
「『攻め』続けすぎると参加者は辟易してくる」
どんなしっかりとした説明や答弁も、過ぎたれば何とやらです。
これには、適度なタイミングで「~ですよね?」「ここまで何か疑問はありますか?」など、相手に対する問いかけを挟むのが有効です。
最後に「終わり方」に関するコツを。
この「終わり方」については後日別途書きますので、ここでは「聞かれる会議」で役に立つものを一つだけ。
それは、
「必ず『攻め』で終わり、締めの言葉をはっきり言う」
です。
途中どれだけ『守り』ばかりだったとしても、しっかり誤ってから、次ちゃんとやります!と『攻め』て『以上です!』と締めれば、会議はすんなり終わることが多いものです。
この、締めの言葉をうまく使って、会議をうまくコントロールしましょう。
登録:
コメントの投稿 (Atom)

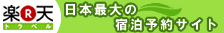
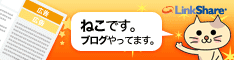


0 件のコメント:
コメントを投稿