今回は「双方で何かを決定する」会議についてです。
当然ですが、前回までの内容がこのタイプの会議ではすべて必要になります。
例えば、
「事前準備」(その2参照)
「最重要ステークホルダーは誰か」(その3参照)
「攻守のフェーズの切り替え」(その4参照)
「聞き出した内容は、必ずその場で自分で整理して、参加者全員に確認する」(その3参照)
「締め方(会議の終わり方)」(その4参照)
などです。
ですので、ここではこれまで触れなかった部分を中心にまとめていこうと思います。
当たり前ですが、このタイプの会議の開始時点では「結論」が合意できておらず、会議の目的は「結論を出す」ことになります。
ですので、大きく会議の行方を握るのは「自分なりの結論を持った人」になるでしょう。
この観点で会議を見てみると、いろんなパターンが見えてくると思います。
例えば、
「結論(=落とし所)を持った人がいない場合」
発言がなかったり、逆に議論が拡散したりして、結果的に意味のない会議になりがちです。
「結論を持った人が1人の場合」
必要な議論が行われずその人の都合のよいその場の結論が出され、後々問題となったりします。
「自分なりの結論を持った人が多すぎる場合」
会議が紛糾したり、利害の絡み合った綱引きになったりして結論がでにくい会議となります。
まず、会議の前半で、参加者の考えている落とし所を聞き出しましょう。
いわゆる「腹の探り合い」です。
まぁ、エンジニアリングの世界ではあまりコソコソせす、どーんと聞いてしまうのが手っとりばやいと思いますが、契約や費用などナーバスな問題がからむ場合は、より「政治的な」駆け引きが必要となるでしょう。
が、そのあたりはまた別の機会に。
参加者の思惑や、会議のパターンが見えてきたところで、実際のコントロールの話に入るわけですが、その際に、自分がどの立場で会議に臨むのかで必要なテクニックは変わってきます。
次回から、自分が落とし所を持っている場合と持っていない場合のコントロールテクニックを書いていこうと思います。
2009年1月22日木曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)

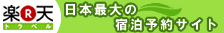
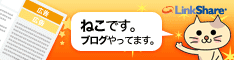


0 件のコメント:
コメントを投稿